
桜満開ですね!
今日はあなたの会社をつぶす10の方法というお話です(笑)
政治家や経営者の方は必読です!
『貞観政要』(じょうがんせいよう)という本は北条政子や徳川家康、明治天皇もが愛読したという帝王学の教科書で名著です。初心者の方向けにもいろいろな本が出ているのでぜひ読んでみてください。
以下は帝王学の三原則として有名ですね
<<帝王学の三原則>>
1. 原理原則を教えてくれる師を持つこと。
今でいう「メンター」を持つこと。
2. 良き幕賓(ばくひん)を持つこと。
「幕賓」とは、出仕することを好まず一種の浪人的風格と気骨をもった人物のことで今でいう「アドバイザー」のような人のこと。
3. 諫言(かんげん)してくれる部下を持つこと。
上司を諫めることを言ってくれる人が必要。昔は諫めると処刑されてしまう例が多かったがそれでは国は滅んでしまうということ。
帝王学なんて役に立たないという人もいますが短期的に成功するためには確かに必要ではないかもしれません。しかし歴史をひも解くとたとえばこの世の春の栄華を極めていても最期に悲劇が待っていることが多いのです。かならず報いを受けるということなのでしょう。日本でも同様の事が起きていたなぁと実感します。
貞観政要は、唐の二代皇帝・太宗(たいそう)とその家臣たちとの政治に関するやり取りをまとめたもので、中国唐代に呉兢が編纂したとされる太宗の言行録です。「貞観」は太宗の在位の年号で「令和」のようなもので、「政要」は「政治の要諦」のことです。
とくに面白いのは皇帝太宗ははじめはきちんとしていたにもかかわらず治世開始から13年後にして悪い行いが現れ始めたため、家臣の魏徴(ぎちょう)が諫めた「魏徴の諫言十箇条」です。これはなぜ皇帝は有終の美を飾れないのかという理由を10個述べたものです。
なかなか皇帝にここまで言える人はいないと思いますが、長年続くためにはまさにこうした諫言を言ってくれる部下をもつことだと本書では指摘しています。
お友達や茶坊主で固めては本当の情報が入ってこなくなりやがて国や会社が衰退して滅んでいく理由を端的に指摘しているので今日でもとても参考になる内容ではないかと思うのでご紹介しましょう!
はじめに
私(魏徴:ぎちょう)が歴史上の王朝を見ると、最初の頃は、素朴を第一にして華美を抑え、忠良な家臣を尊んで邪な者を卑しみ、贅沢をせずに倹約をし、生活必需品を大事にして珍しい品物を卑しんでいました。
しかしある程度軌道に乗ると、それに反した行動を取ることが多いようです。
それは皇帝が最高の地位にあり、全国の富を手に入れ、誰も逆らう者はなく、命令に誰もが従い、公事に私情が挟まれ、礼儀が欲望で欠けてしまうからではないでしょうか。
古語に「知ることが難しいのではなく、行うことが難しい。行うことが難しいのではなく、きちんとやり遂げることが難しい」とありますが、その通りです。
私が考えますに、陛下が皇帝になられた初めのころは、欲望を抑え、倹約し、国の内外が安らかで、非常に世が治まっていました。
しかし最近は以前とは違って初心をお忘れになり、終わりを全う(最後まで立派に成し遂げること)できないのではないかと案じます。
私が聞いたところを連ねますと、次のようでございます。
高級品を好むようになった
陛下は最初のころは無為無欲でしたが、最近はだんだんそうでなくなってきました。
陛下のお言葉だけ聞けば聖者を超えていますが、実際の行動は凡帝以下です。
こう申しますのは、陛下は駿馬を万里の彼方まで探し求め、珍宝を国外から買い求め、それを運ぶ行列を見た民衆は怪しみ、異民族からはバカにされています。
これが終わりを全うできない第一の理由です。
民に軽々しく労役を課すようになった
陛下は最初のころは民を見るときにはケガ人を見るように優しく、働く様子を見れば我が子のように愛し、簡素を常とし、大掛かりな土木工事はなさいませんでした。
しかし最近の陛下は贅沢を好んで節約を忘れ、軽々しく民に労役を課し、「民はやることがなければ怠ける。労役をさせれば扱いやすくなる」とおっしゃいます。
古来から民が怠けて国が傾いた例はありませんのに、どうしてそのようにおっしゃって労役を課すのでしょうか。
国のためを思ってのお言葉ではないと思われます。
これがどうして民の幸福を考えてのことだと言えましょう。
これが終わりを全うできない第二の理由です。
豪華な宮殿造営をさせるようになった
陛下は最初のころは自分が損しても民の利益を優先されました。
しかし最近の陛下は自分の欲のために民を使っています。
節約の気持ちがだんだんなくなり、贅沢の気持ちがだんだん増してきています。
口では「民のことを考えている」とおっしゃっていますが、実際は自分の楽しみに熱心です。
宮殿造営を諫める声を防ぐために「これを造らないと不便なのだ」と事前におっしゃいますが、そう言われて諫める家臣がありましょうか。
そうおっしゃるのは相手の口を塞ぐためであって、良いことを選んで行う者とどうして言えましょうか。
これが終わりを全うできない第三の理由です。
君子を遠ざけ、小人を近づけるようになった
陛下は最初のころは名誉と礼節に励み、人をひいきせず、善人と親しみ、君子を愛し、小人は遠ざけていました。
君子とは理想的人格者で高位高官のことです。
小人とは品性のいやしい人で欲深いつまらぬ人物のことです。
しかし最近の陛下は口では小人をバカにして、君子を大事にしているようですが、実際は君子を遠ざけ、小人を近づけています。
近づけば悪い点が見えなくなり、遠ざければ良い点を知ることができなくなります。
君子の良い点を知ることができなければ疎遠になっていきます。小人の悪い点を見ることができなければ親しくなっていきます。小人と親しくして世を治めることはできません。
君子と疎遠になって国を興すことはできません。
これが終わりを全うできない第四の理由です。
農業を軽視し工業ばかり重視するようになった
陛下は最初のころは黄金や宝石を投げ捨て、質素な暮らしをされていました。
しかし最近の陛下は珍しいものを好み、手に入れにくいものでも遠方から取り寄せ、工匠に精巧な品を作らせ続けて止むことがありません。
陛下が贅沢を好みながら民には質素を望んでも無理なことです。
工業がますます盛んになりながら、農業も豊かになることができないことは明らかです。
これが終わりを全うできない第五の理由です。
口のうまい人の言葉に騙されて人を判断するようになった
陛下は最初のころは賢者を探し求め、善人が推薦した者を信じ、長所を用い、まだ賢者を求めることが足らないのではと心配していました。
しかし最近の陛下は自分の好き嫌いで人を判断しています。
多くの人が賢者だと推薦した人でも、誰か一人が悪く言えばその人を採用しません。
また長年信用して仕えた家臣でも、少し疑っただけで遠ざけてしまいます。
人を悪く言う人が、必ずしも賢者と言われている人よりも信用できるわけではありません。
少し悪く言う人があったからといって、長年仕えた者を遠ざけてはいけません。
君子の心は善を行い、徳を治めようとするものです。
小人の性は他人の悪口を好んで、自分のことばかり考えるものです。
しかし陛下は相手のことを深くお調べにならないで、口先の表面だけで相手の心を判断しています。
これでは君子は疎遠になり、小人が近づくことになります。
そのため家臣たちは失敗さえしなければいいと思い、能力を存分に尽くそうと思わなくなります。
これが終わりを全うできない第六の理由です。
政務をせずに遊びに出かけるようになった
陛下は最初のころは楽しみを求めることなく、狩りの道具を捨てて、狩り遊びができないようにしていました。
しかし最近の陛下は狩り遊びにふけるようになり、民からは批判され、鷹や猟犬の貢物が遠方から届けられるようになりました。
あるいは狩場が遠いからといって、朝早くでかけて夜遅く帰ってきます。
馬を走らせることを楽しみとし、不慮の事故や災難のことを考えていません。
これではたとえ外出時に不測の事態があってもお守りすることができません。
これが終わりを全うできない第七の理由です。
家臣をないがしろにするようになった
陛下は最初のころは敬う心をもって家臣と接し、陛下の恩は家臣全員に届き、家臣の心は陛下に届いていました。
そのため家臣はみな、全力で使命を果たそうとし、心を隠すことはありませんでした。
しかし最近の陛下は家臣をないがしろにするようになりました。
地方官が地方の状況を申し上げようと参上しても陛下はお会いにならず、お会いになっても地方官の希望をお取り上げになりません。
そうかと思えば突然、家臣のささいな悪い点を詰問します。
これではどんな優秀な者でも、忠心を述べることができません。
そうなりますと陛下と家臣が心を一致させて、安定した世の中を望むことは難しいでしょう。
これが終わりを全うできない第八の理由です。
傲慢になり欲望が大きくなった
陛下は最初のころは努力を怠らず、自分の意志を曲げて人に従い、自分に足らないところがあるかのようにしていました。
しかし最近の陛下はいばってわがままになり、ご自身の功績の大きいことを理由に過去の皇帝を軽蔑し、ご自身の賢さを理由に家臣を見下しています。
これは傲慢の心が大きくなったからです。
そのためやりたいと思ったら心の通りに行動します。
たとえ諫めに従うことがあっても、やりたいと思ったことを忘れることができません。
これは欲の心が大きくなったからです。
心では楽しみのことばかり考え、どこまで楽しんでも満足することはありません。
まだ政務の妨げとはなっていませんが、以前のように政務のことばかり考えることはなくなりました。
国内も周辺国も治まっているのに、遠方まで軍隊を行かせて僻地にいる異民族の罪を責めています。これは欲望に際限がないからです。
陛下に近づきなじんでいる者は、みな陛下のご機嫌を取って何か思ってもあえて申し上げません。疎遠な者は御威光を畏れて諫めようとしません。
このようなことが重なれば、陛下のお徳に傷がつくことになりましょう。
これが終わりを全うできない第九の理由です。
民の気持ちを考えないようになった
陛下は最初のころは天災が起こったこともありましたが、家を捨てた者はなく、苦しみを恨んだ者もありませんでした。
これは陛下の憐みの心を皆が知っていたからです。
そのため飢え死にすることがあっても陛下を悪く思う者はありませんでした。
しかし最近の陛下は民に労役をさせ、民はみな疲れ果てています。
工匠に休日返上で働かせ、兵士には仕事の日に別のことをやらせています。
売買の品物を地方から持ってこさせ、運搬人が道に列を成しています。
このため何かのきっかけがあれば暴動が起きやすくなっています。
もしも洪水や日照りのために穀物の収穫ができなくなれば、民たちの心は以前のようにはいかないでしょう。
これが終わりを全うできない第十の理由です。
まとめ
「災難も幸福もどこかからやってくるわけではなく、自分自身が起こすものだ」という言葉があります。
陛下が天下を治め始めて13年の間に、道徳は国内に行き渡り、御威光は国外までとどろき、穀物は豊作になり、学問が興り、民たちはみな官吏となってもおかしくない者ばかりになり、食物は水や火のように豊富になりました。
しかし最近は天災が流行り、日照りになり、地方で被害が出ており、悪者が悪事を行い、城下でも凶悪犯罪が起こるようになりました。
今こそ、この事態に驚いて心配する時です。
賢者の言葉に従い、細かく気を配り、自分の間違いを反省し、過去の皇帝がどのように世の中を治めたかを学んで実行し、失敗の原因を改め、世の中を新しくし、人の考え方を変えれば、天子の位は限りなく続き、天下の人々は幸福になり、災いの心配はなくなるでしょう。
そう考えますと、政治や国家の安否は陛下お一人にかかっています。
平安の世の中の基礎は既に整っていますが、長い間の努力も最後の少しのミスからダメになってしまうものです。
今は千年に一度の時期です。賢明な陛下ならば本当は実行できることなのに実行しないため、取るに足らない私ごときが嘆いているのです。
私はバカなため物事がよくわかりませんが、私が見て感じたことを十箇条にしてお伝え申し上げました。
陛下が間違いばかりの私の言葉を採用し、身分の低い者の意見も参考にしていただけますことを慎んでお願い申し上げます。
私ごときの考えにも少しは得るところがあって、陛下の政務にわずかでも役立てていただけましたら、無礼を申し上げた私が今日死刑になろうとも、国が生まれ変わる日と思えば満足でございます。
太宗の対応
この魏徴(ぎちょう)の諌めを聞いた太宗が言いました。
家臣が主君に仕えるとき、主君の言うことに従うのは簡単だが、逆らうのは最も難しいことである。
そなた(魏徴)は私の耳目や手足となっていつも考えていることを教えてくれる。
私は今、自らの間違いを聞いたが必ず改めよう。そして終わりを全うしたいものだ。
そなたの言葉に反することをしたならば、何の顔(かんばせ)あってかそなたに会えようか。また天下を治められようか。
そなたの諌めはよく考えられていて、正しいと思う。
そなたの言葉を屏風にして朝夕仰ぎ見られるよう、史官に記録させた。
千年後の者が、主君と臣下の正しい道を知ってくれることを願う。
そうして、太宗は魏徴(ぎちょう)に金千斤と馬二匹を贈りました。
リーダーへの教訓
魏徴の十箇条を現代に置き換えて考えてみると以下のようになるかもしれません。
1 高級品を好むようになった
社長がフェラーリや馬を買うようになった
2 民に軽々しく労役を課すようになった
社員が疲弊するほどブラックな会社になっている
3 豪華な宮殿造営をするようになった
高級タワマンの上層階に引っ越したり豪華な別荘を建てたりする
(どっかの自称国際政治学者みたいですね (笑))
4 君子を遠ざけ、小人を近づけるようになった
有能な人物を遠ざけて、怪しい人たちとつるむようになる
5 工業ばかり重視し食の基本である農を軽視するようになった
基幹となる本業を軽視してあたらしことばかり重視する 自給率をあげようとしない政府
6 口のうまい人の口先だけで人を判断するようになった
詐欺師や口のうまい茶坊主やお調子者を優秀だと勘違いして信用してしまう
7 公務をせずに遊びに出かけるようになった
仕事以外の遊びに熱中するようになった 銀座や西麻布に入り浸りでしょうか
8 家臣をないがしろにするようになった
部下に対して傲慢な態度を取るようになった
(どっかの大臣は部下の作った文書を捏造と非難していましたね)
9 傲慢になり欲望が大きくなった
部下の諫言を聞かなくなり、自分のやりたいことばかりするようになった
10 民の気持ちを考えないようになった
社員の本当の気持ちを理解しようとしなくなった
リーダーにとっては耳の痛い話ばかりですが、非常に鋭い指摘だと思います
どこかの国の国会議員やワンマン社長さんたちはぜひ参考にしてみてください(笑)
★カール経営塾動画★では経営MBAのプラットフォーム戦略(R) 経営戦略からマーケティング、ファイナンス、起業関連など様々な動画講座、無料講座も登場して大人気です!ぜひチェックしてみてください!
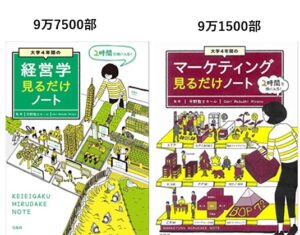
How Can We Help?
-
経営学用語
- AIサーバー GPUサーバー
- AI半導体AIアクセラレーター、ファウンドリー
- AI開発プラットフォーム
- GPU(画像処理半導体 Graphics processing unit)
- RAG (Retrieval Augmented Generation、検索拡張生成)
- インスタンス
- クラウドコンピューティング
- システムインテグレーター (Sler)
- シンギュラリティ (singularity)
- スケーリング則(Scaling Laws for Neural Language Models)
- ディープフェイク Deep Fake
- トランスフォーマー
- ファインチューニング
- マネージドサービス
- マルチモーダル
- 動画生成AI「Dream Machine」
- 大規模言語モデル (LLM) パラメーター数
- 生成AI
- EBITとEBITDAの違い
- NFT(Non-Fungible Token 非代替性トークン)
- SPAC スパック Special Purpose Acquisition Company 特別買収目的会社
- 「銀行業高度化等会社」とは
- 【決定版】企業価値算定DCF法CAPM ベータ値WACCとは
- オプション取引 コールオプション&プットオプション Option
- オープンAPI Open API
- キャッシュ・コンバージョン・サイクル(CCC)とは
- スワップ取引とは SwapTransaction
- テーパリング Tapering
- デリバティブとは derivative
- ハードフォークとソフトフォーク(暗号資産 仮想通貨)
- バリュー・アット・リスク Value at Risk(VaR)
- ビットコインとブロックチェーン Bitcoin&Block chain
- フィンテックベンチャー
- ブラック・ショールズ・モデル B&S Model
- リアル・オプション real option
- 一株当たり純資産とは Book-value Per Share(BPS)
- 会社のねだんの決め方~企業価値算定3つの方法 Valuation
- 会計とファイナンスの違い Accounting&Finance
- 債券とは 格付けとは
- 先渡取引とは Forward transactions
- 固定比率とは Fixed ratio
- 固定長期適合率とは fixed long term conformity rate
- 売上高営業利益率とは Operating Profit Ratio
- 売上高売上総利益率とは
- 売上高経常利益率とは ordinary profit ratio
- 当座比率とは Quick assets ratio
- 投下資本利益率(ROI)とは Return on investment
- 投資銀行(Investment Bank)&証券化
- 株主資本比率(自己資本比率)とは Capital ratio, Equity ratio
- 株価収益率(PER)とは Price Earnings Ratio
- 株価純資産倍率(PBR)とは Price Book-value Ratio
- 流動比率とは Current Ratio
- 現在価値とは何か? What is Present Value?
- 総資本回転率とは total asset turnover
- 総資産利益率(ROA)とは Return on assets
- 負債比率とは Debt Equity Ratio
- 財務諸表とは?BS PL CS
- 責任銀行原則 Principles for Responsible Banking
- 資本(自己資本)利益率(ROE)とは Return on Equity
- 配当性向とは Payout Ratio
- 金融工学とは financial engineering
- 銀行の機能とは? 金融仲介・信用創造・決済機能
- 1株当たり純利益とはEarnings per Share(EPS)
- 3つのコーポレート・ファイナンス Corporate Finance
- Alexa Rank(順位)
- DaaS Device-as-a-Subscription
- DSP SSP RBT DMP
- KGI KSF KPIの設定
- LPO Landing Page Optimization
- PASONA(パソナ)の法則 Problem Agitation Solution Narrow down Action
- RFM分析 recency, frequency, monetary analysis
- ROS/RMS分析 ROS/RMS Analysis
- SEOとSEMの違い Search Engine Optimization Search Engine Marketing
- 【まとめ】インターネット広告における主な指標 advertisement indicator
- アトリビューション分析 attribution analysis
- アドネットワーク advertising network
- アドベリフィケーション Ad-verification
- アンバサダー、アドボケイツ、インフルエンサー Ambassador Advocates Influencer
- インターナルマーケティング7つの方法 Internal Marketing
- インバウンドマーケティング inbound marketing
- エスノグラフィ(行動観察法)ethnography
- ゲリラ・マーケティング Guerrilla marketing
- ゲーミフィケーション Gamification
- コトラーの「純顧客価値」とは Net Customer Value
- コトラーの競争地位別戦略 Kotler’s Competitive Position Strategy
- コピーライティング Copywriting PREP法
- コーズ・リレイテッド・マーケティング Cause-related marketing
- サービスマーケティング service marketing
- サービス・ドミナント・ロジック Service Dominant Logic
- サービス・プロフィット・チェーン Service Profit Chain
- サービス・マーケティングの7P Service marketing7P
- ショウルーミング Webルーミング showrooming
- ソーシャルグラフ social graph
- ソーシャルリスニング・傾聴 Social Listening
- ソーシャル戦略 Social Platform Strategy
- ダイレクト・マーケティング Direct Marketing
- トリプルメディア Triple Media
- ネイティブ広告 Native advertising
- ハルシネーション ハルシネイション Hallucination
- ハワード=シェス・モデル Howard & Sheth model
- バートルテスト Bartle Test
- プログラマティック・バイイング programmatic buying
- プロダクト・プレイスメント Product Placement
- ペルソナ(persona)
- ホリスティック・マーケティング Holistic Marketing
- マズローの欲求5段階説
- マーケットシェア&マインドシェア ポジショニング戦略 positioning strategy
- マーケティングとは What is Marketing?
- マーケティングの本質とは Essence of Marketing
- マーケティングの起源 Origin of marketing
- マーケティング戦略策定プロセスの全体像 Marketing Strategy
- マーケティング戦略4P(マーケティング・ミックスMM) Product Price Place Promotion
- ラテラル・マーケティング Lateral Marketing
- リスティング広告 検索エンジン連動型広告 PPC広告 Paid Listing
- 多変量解析 multivariate statistics
- 定量分析手法多変量解析ROSRMS
- 期待不確認モデル expectation disconfirmation model
- 炎上マーケティング flaming marketing
- 経験価値マーケティング Experiential Marketing
- 行動ターゲティング広告とリターゲティング BTA behavioral targeting advertising,retargeting advertising
- 製品ライフサイクル Product life cycle
- 顧客生涯価値(ライフタイムバリュー)LTV(Life time Value)
- DAGMAR理論 DAGMAR Theory
- SERVQUAL(サーブクオル)モデル
- BPR(ビジネスプロセス・リエンジニアリング)
- DellのBTO Build To Order
- EVA Economic Value Added
- MECE(ミッシー)
- PDCA &BSC&OODA
- PEST分析 ペスト分析
- SDGsとは?
- SMART Specific、Measurable、Achievable、Related、Time-bound
- SWOT分析とクロスSWOT分析
- VRIO分析
- ★BCGのアドバンテージマトリックス Boston Consulting Group's Advantage Matrix
- ★マッキンゼーの7Sフレームワーク McKinsey 7S framework
- 「帰納法」Inductive Approachと「演繹法」Deductive Approach
- 【コア・コンピタンス】とは 模倣可能性・移転可能性・代替可能性・希少性・耐久性
- アンゾフの製品市場マトリクス(マトリックス)成長ベクトルProduct-Market Growth Matrix
- イノベーター理論とキャズム Innovation Theory & Chasm
- エフェクチュエーション(effectuation)&コーゼーション(causation)
- コーペティション経営 Co-opetition Strategy
- サンクコスト(埋没費用)バイアス
- シナリオプランニング Scenario planning
- タイムベース競争戦略 time-based competition
- デコンストラクション deconstruction
- デザイン思考 design thinking
- デジタル・フォレンジック Digital forensics
- デジュリスタンダード&デファクトスタンダード 2つの標準化(対義語) 具体例
- ネット・プロモーター経営(NPS)Net Promoter Score
- ハインリッヒの法則 Heinrich's law
- ピラミッドストラクチャー(構造化)
- フリー戦略
- フレームワークとは Framework
- ブルー・オーシャン戦略 Blue Ocean Strategy
- ポーターのCSV Creating Shared Value
- ポーターのバリューチェーン(価値連鎖)分析
- ポーターのファイブフォース分析 Porter five forces analysis
- ポーターの3つの基本戦略 Porter’s three generic strategies~ lower cost, differentiated focus
- ランチェスター戦略 弱者の戦略
- リバース・イノベーション Reverse Innovation
- 仮説思考 hypothesis thinking
- 全社戦略・事業戦略・機能別戦略 Corporate Strategy Business Strategy Functional Strategy
- 新商品や新サービスを作り出す15の発想法
- 暗黙知と形式知(SECIモデル)
- 破壊的イノベーション Disruptive innovation
- 魚は頭から腐る
- 3C分析(Customer, Competitor,Company )


